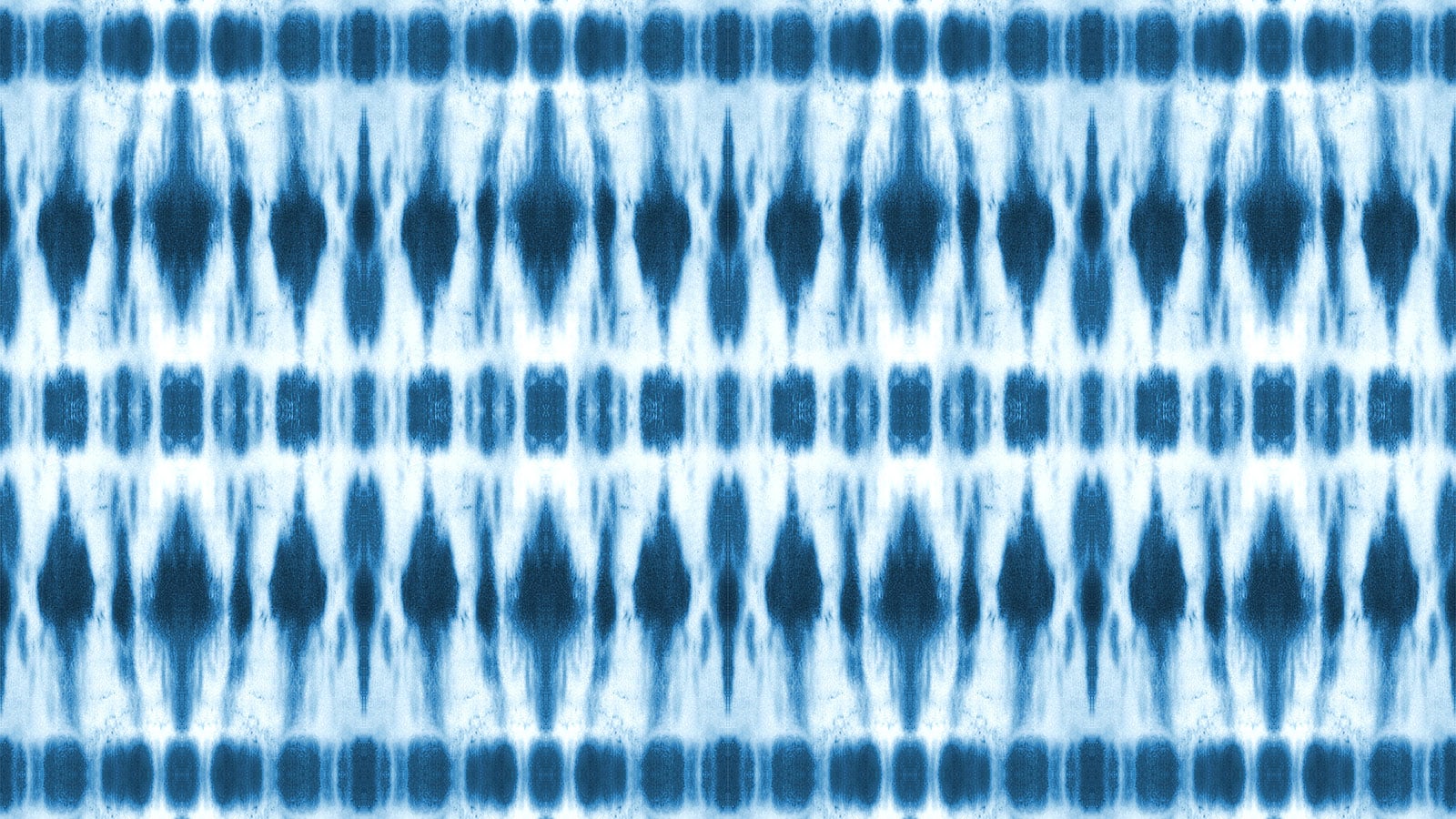本建てと化学建ての染色性の違い
ハイドロや苛性ソーダを使用しない『本建て正藍染め』と、インド藍などを使用した『ハイドロ化学建て』では浸透性に違いがあります。
例えば雪花絞りでは、ハイドロ化学建てでは浸透が良いため中心の方の絞りの際までしっかりと色が入るのですが、本建て正藍染めではなかなか同じようにはいきません。
この違いについて化学的な検証を行ったレポートがございましたのでご紹介いたします。
レポートでは天然藍の方がインジゴ分子の会合が大きいことに由来するという結論に至っています。補足すると還元液中ではインジゴはロイコ体として存在するので、ロイコインジゴの分子会合の差といえるでしょう。
この会合の違いにより、滲み(浸透性)だけでなく色相や色の冴え、ムラなどに違いがでることを化学的に検証した興味深い文献ですのでぜひご覧ください。
本建てで浸透性を高める方法は…わかりません。
本建て正藍染めで化学建ての様に浸透性を高めることができないか、藍液に界面活性剤や染料分散剤を添加することで解決を試みたことがあります。
しかし化学的な染色助剤を添加したら、それはもはや正藍染めとはいえません。
天然素材でその役割を果たす何かを見つけられれば良いのですが・・・どなたかご存知であればぜひ教えてください。
藍液の調整に日本酒を使用すると浸透性が上がるような『気がします』(気のせいかもしれません)。アルコールが会合に影響を与えている可能性を考え調べてみましたが、藍染における日本酒の役割について化学的に説明がなされている文献が少ないため確認ができません。
またいつか日本酒と浸透性の関係を試験してみたいと思います。

本建てと化学建ては使い分ければ良い
正藍染めには正藍染めの良さがあります。化学建てには正藍染めにないメリットがあります。両者は異なるものとして使い分けることで、それぞれの特徴を作品に活かせれば良いと弊社は考えます。
「化学建ては偽物」のように、とかく「どちらが良い悪い」で語られます。『化学建て』で染めた製品を『本建て』と表記し騙すような人がいるので「化学建ては悪者」のような印象につながっているのだと思いますが、目的に応じ『本建てであること』『化学建てであること』を明記し使い分けるのであれば、そこに大きな問題はなく、柔軟に考えれば良いと思います。